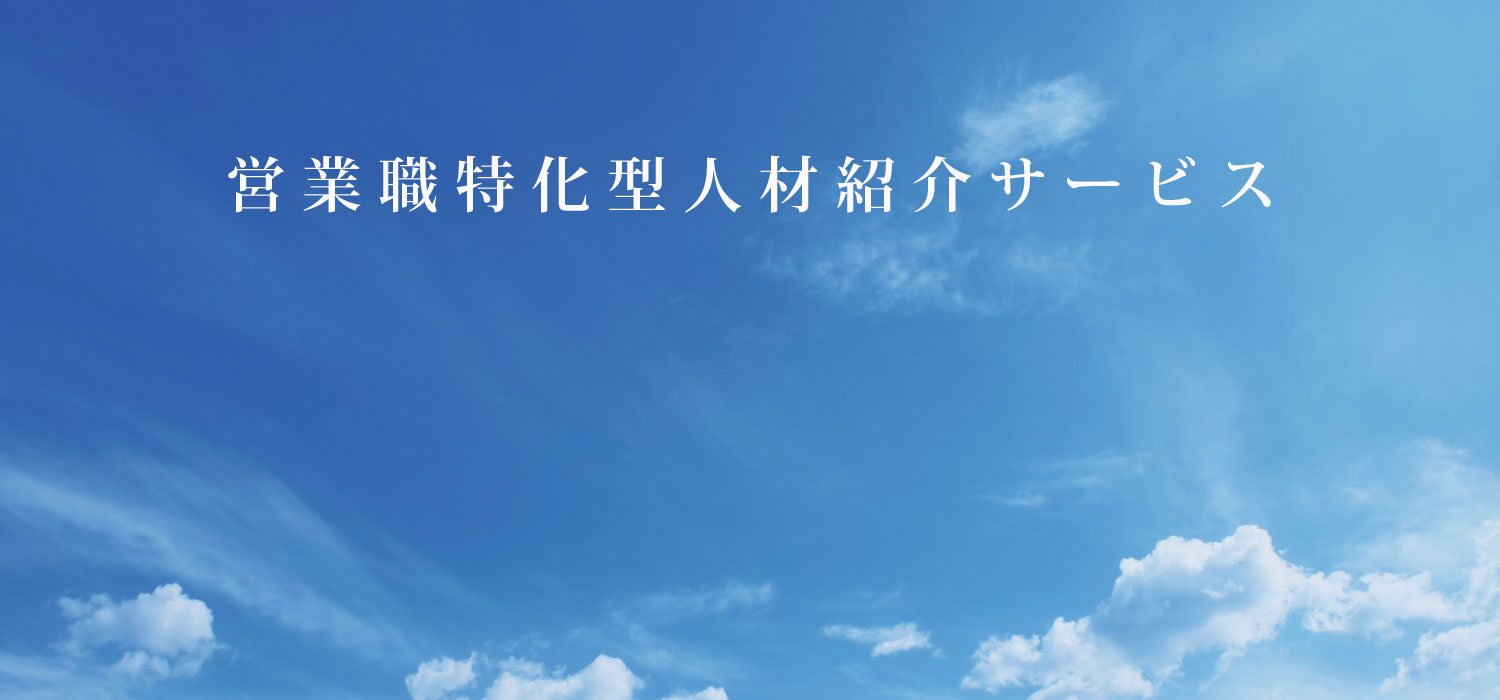理化学研究所(本部:埼玉県和光市)は6月18日、富士通とともに基幹スーパーコンピューター「富岳」の後継機を開発すると発表した。富士通はシステム全体の基本設計を担当するほか、CPU(中央演算処理装置)も新規に開発する。富士通が担う基本設計の期間は2026年2月27日まで。2030年頃に世界最高水準の性能での運用開始を目指す。
「新技術・新開発」カテゴリーアーカイブ
ヤンマーとスシロー 養殖ブリ 遠隔でエサやりシステム実証
大林組, アイシン ペロブスカイト太陽電池実用化へ実証実験
ミズノ, カネカ 人工芝に水中分解素材 海洋へのプラごみ削減
ユニ・チャーム, 王子と協働 パームヤシ空果房使用段ボール
大成建設, ユーグレナ「サステオ」建設現場に初導入, 脱炭素
リニア中央新幹線工事 愛知県でシールドマシン使い本格化
遺伝性アルツハイマー病 iPS創薬で見つけた薬で最終治験
京都大学グループ、大阪の医薬品メーカー、東和薬品は6月3日、遺伝性のアルツハイマー病治療について、iPS細胞を薬の開発に応用する「iPS創薬」と呼ばれる手法で効果がみられた、パーキンソン病の既存の治療薬「ブリモクリプチン」にアルツハイマー病と関係する物質を減らす効果があることを見つけ、この実用化を目指し最終段階の治験を始めたと発表した。
グループはこれまで特定の遺伝性アルツハイマー病の患者を対象に治療を行ってきた。その結果、ブリモクリプチンを投与した患者は認知機能の低下など、症状の進行が抑えられる傾向があったという。そこで実用化に向けて、東和薬品が患者24人を対象にした最終段階の治験を5月から始めたことを明らかにした。
この最終治験は2028年3月まで行う予定で、有効性や安全性が確認できれば、治験が終了してから1年程度で国に承認申請したいとしている。
川崎重工など3社 液化水素運搬船の建造体制構築で協業
KDDI「スターリンク」活用のドローン運航 年内に実証実験
KDDIは5月29日、年内に米宇宙企業スペースXの衛星通信網「スターリンク」との直接通信を活用して、ドローンを運航する実証実験を行うと発表した。地震など災害時の活用が期待され、2026年3月までの実用化を目指す。
KDDIは10月以降に順次、全国1,000カ所にドローンが離着陸する拠点となる機器を整備する。震災からの復興で包括連携協定を結んでいる石川県から導入を始め、経営に参画しているローソンの店舗や市役所などにドローンを配備する。電線など社会インフラの監視や建設現場の作業確認、災害時の捜索活動などで使用することを想定。スターリンクと直接通信すれば、山間部や離島などでも簡単にドローンを運航できるようになる。